こんにちはFP消防士です。
今回は、防火管理者についてのお話です。
防火管理者とは、消防法において一定の条件を満たす建物で必要となります。
防火管理者となった方は、その建物内の防火に関する管理を行います。
この記事は
防火管理者とは何か??
防火管理者の業務内容は??
このようなことが知りたい人向けの内容となっています。
結論
防火管理者といったい何で、どのようなことを業務としているのか??
防火管理は資格が必要で、防火に関する責任者!
防火に関する業務全般!!
防火管理者は、防火に関する業務全般を行いますが、あとで詳しく解説してきます。
防火管理者が必要な防火対象物
まずは、防火管理者が必要な防火対象物についてお話していきます。
全ての防火対象物に防火管理者が必要となる訳ではありません。
その、防火対象物の用途、規模、収容人員によって変わってきます。
用途とは、防火対象物がどの用途に区分されるかを見ます。
消防法施行令別表第1では、1項から20項まであり細く区分されています。
例えば、飲食店は3項ロ、小学校は7項のように区分されています。
規模は、防火対象の床面積等を表しています。
あと、収容人員とは何か?
収容人員とは人がどのくらい入るかを算定します。
これは、用途にとって算定方法が異なります。
従業員数、椅子の数、床面積を一定の数で割った数等、様々です。
例えば、椅子でも固定椅子かどうかでも変わる場合があります。
防火管理者が必要なもの
防火管理者が必要な防火対象物について簡単に説明していきます。
1 自力避難が困難なものが入所する社会福祉施設を含む防火対象物のうち、全体の収容人員が10人以上。
2 不特定多数の人が出入りする防火対象物(特定用途)で収容人員が30人以上。
(劇場、飲食店、スーパーマーケット等が対象となります。)
3 不特定多数の人が出入りしない対象物(非特定用途)で収容人員が50人以上。
(事務所、学校、工場等が対象となります。)
4 新築工事中の建物で収容人員が50人以上。
(総務省令で定めるもの。)
5 建造中の旅客船で収容人員が50人以上。
(総務省令で定めるもの。)
6 敷地内の屋外タンク貯蔵所や屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が1,000倍以上。
7 指定可燃物を貯蔵、取り扱う防火対象物で床面積の合計が1,500㎡以上。
8 50台以上(収容人員50人以上)の車両が駐車する屋内駐車場。
防火管理者の資格の種類
防火管理の資格には2種類あります。
◯甲種
用途、規模、収容人に関わらず全ての防火対象物の防火管理者になれます。
◯乙種
収容人員が30人以上で300㎡未満、収容人50人以上で500㎡未満の防火対象物で防火管理者になれます。
防火管理者になるには資格を取得する必要がありますが、講習を受講すれば資格取得となります。
甲種防火管理者講習は2日間、乙種防火管理者講習は1日となっています。
また、防火管理者には管理的・監督的地位にある人となります。
防火管理者選任届出が必要
防火管理者に選任された際には、消防署への届出が必要です。
届出は、管轄の消防本部のホームページ等でダウンロードし、最寄りの消防署に届出をしてください。Webで届出できる消防本部もあるので確認してみてください。
ここで必要な届出は、防火管理者選任届出と消防計画書が必要となります。
防火管理者選任届出には防火管理者の免状のコピー等が必要です。
消防計画書は避難計画、緊急連絡先、日常の防火点検要領、消防訓練・消防設備点検日程等を記載する必要があります。
消防本部によって様式等に若干の違いがあるので、管轄の消防本部に従って記載してください。
記載内容等、分からない箇所も多くあると思います。その際には、最寄りの消防署で相談してください。
再講習について
防火管理者の再講習が必要な場合があります。
収容人員が300人以上の特定防火対象物に選任されている新規に甲種防火管理者が該当となります。
1 選任日から講習修了日から4年以内(講習修了日から最初の4月1日から5年以内)
2 選任日が講習修了日から4年を超えている(選任日から1年以内)
再講習が必要となる場合があるので注意してください。
防火管理者の業務
防火管理者の業務内容を簡単に説明していきます。
◯ 消防計画と作成
先程、説明した通りです。
下記の内容をまとめ、消防計画を作成し、管轄の消防署に届出を行います。
記載要領等が不明な場合は、消防署に相談してください。
◯ 消防訓練の計画と実施(避難・通報・消火)
防火対象物によって、訓練の回数が定められています。
特定防火対象物は、消火訓練と避難訓練は年2回以上。
非特定防火対象物は、消防訓練に定められた回数となっています。
特定防火対象物、非特定用途防火対象物ともに通報訓練は消防計画に定められた回数となっています。
消防訓練の日程を決めたり、計画を行います。
消防署に事前連絡すれば、消防職員に指導してもらうことも可能です。
◯ 消防用設備の維持管理(点検・整備)
消防用設備の点検や整備を行います。
点検や整備といっても、資格が必要な設備もありますので基本的には目視で不備がないかを確認することになります。
また、消防設備士のよる点検等の段取りを行ったりします。
◯ 防火上必要な設備等の維持管理(点検・整備)
防火上必要な設備等の点検や整備を行います。
これも、基本的には目視で不備がないか確認することになります。
例えば、防火扉の開閉に支障がないか確認したりします。
◯ 火気の取り扱いの監督
火を使う設備がある場合には、その取り扱いの監督を行います。
点検簿等を作成し、保管しておくことで消防の立入検査の際に防火管理業務の確認を消防側もスムーズ実施することができます。
◯ 収容人員の管理
収容人員によって、消防用設備の設置の有無が変わる場合等もあります。
収容人員の管理も防火管理者にとって必要な業務です。
防火管理業務とは?
防火管理業務は、日常の業務に付随して行われる業務となるので、業務量の負担が増えるのは確かです。
ただ、防火管理は火災予防上必要なことですので防火管理者に選任された方は、しっかりと防火管理業務を行いましょう。
まとめ
今回は、防火管理についてお話しました。
防火管理について少しでも理解していただけたら幸いです。
まとめです。
防火管理者の必要かどうかは防火対象物の用途、規模、収容人員による。
防火管理業務は火災予防上重要な業務である。
以上です。

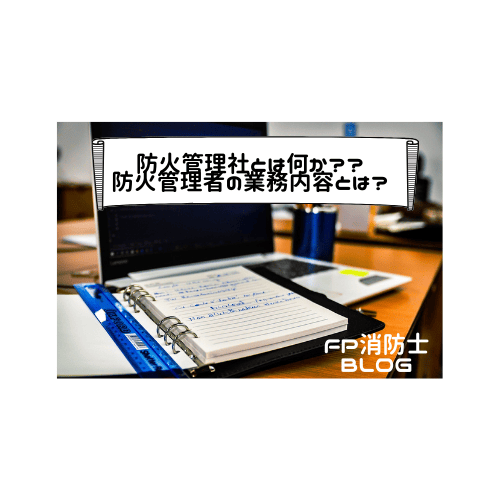
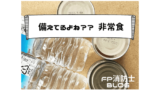
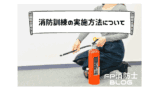
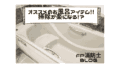
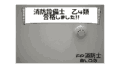
コメント