こんにちは、FP消防士と言います。
この記事は
消防士になりたいけど、どうすればなれるの?
消防士になるための手順が知りたい!!
このようなことが知りたい人に向けての記事となっています。
では、消防士になるための手順を消防歴11年目の現役消防士が解説します。
結論
消防士になるには地方公務員試験の消防職に合格することです。
消防士になるためには、まず各自治体の採用試験の消防職に合格しなければなりません。
消防士は地方公務員になりますので、採用試験では地方公務員の試験を受けないといけません。
倍率は各自治体によって大きな差が出ます。
消防本部よっては、倍率は2〜3倍のところもあれば、10倍〜20倍のところもあります。
私が採用試験を受けた時で倍率は20倍くらいでした。
採用にあっては、もちろん合格者上位から採用されます。
そして公務員試験を突破し、合格すると晴れて『消防士』になれます!
まず消防士になるための手順を解説していきます。
採用案内のチェック
自分が受験したい消防本部のホームページや広報誌等を確認して、採用案内や採用試験の申込み方法の確認をします。
自治体ごとに採用日程や申込み方法が異なりますので要確認が必要です。
受験願書は基本的には郵送やインターネットから入手可能です。
高校生の方は、先生にお願いして願書を取り寄せてもらうこともできると思います。
直接、消防署に取りに行き、未来で働く職場の雰囲気を味わうのもいいかもしれませんね。
受験願書を記入したら、期日内に提出しましょう。
私は申込みを忘れており、試験申込み最終日に郵便局までダッシュした記憶があります。
期日は余裕を持って提出しましょう。
採用試験
消防士になるためには地方公務員試験を受ける必要があります。
消防士を受ける時にどんな試験があるのか全くイメージがつきませんよね。
少しでもイメージが湧き、対策ができるよう解説していきます。
公務員試験は各自治体によって異なりますが、筆記試験、体力試験、面接試験で分かれているところ多いと思います。また、一次試験(筆記試験)と二次試験(体力試験)のように分けて試験を実施するところもあります。
消防本部によって違いがあるので、必ず確認しておきましょう。
参考までに、私の消防本部の大まかな試験スケジュールは以下の通りです。
1次試験
教養試験(一般教養、文章理解、数的処理)
体力試験(腕立て伏せ、上体起こし、懸垂、反復横跳び、100m走、握力、etc…)
作文試験
適正試験
2次試験
口述試験
身体検査
※試験内容は自治体によって異なります。自分が受験する消防本部を確認しましょう。
教養試験
教養試験の内容は高卒程度の内容となっていますが、ただ範囲がとても広い。
簡単に説明すると今まで学校で習った範囲が試験範囲みたいな感じですかね。
その中でも、文章理解や数的処理は公務員試験の解答数に占める割合は6割程度もあります。
公務員試験では、この文章理解や数的処理の問題をどれだけ解くことができたかが合格につながります。
なので、文章理解と数的処理を重点的に対策をして試験に挑む!!これが重要です。
私も採用試験対策として公務員試験の過去問をひたすらに解いた記憶があります。
そして、教養試験と体力試験等の合計点が自分の合格を左右する点数となるわけです。
教養試験は1点でも多く得点することが大事になり、体力試験も同様です。
例えば、1回でも多く懸垂を、0.1秒でも速く走る、といった気持ちで挑みましょう。
体力試験
体力試験の内容も自治体によって差が出ます。
なので、何度も言いますが自分が受ける自治体の試験内容を必ず確認しましょう。
まず、走る系の種目は長距離か短距離か?
どっちもあるのか??
これ結構大事ですよね??
長距離と短距離全然違いますからね。
長距離とは言え、シャトルラン?1500m走?5分間走?このようなことがあるので確認が重要です。
後は、懸垂であったり、腹筋であったり、柔軟系の測定のあったりします。
とりあえず、試験前までに体作りに努めましょう。
作文試験
題材が出され、それについて作文を書きます。
題材は様々で消防に関することから地域防災、またはチームワークに関すること、etc…。
作文試験対策も必須です。
作文が無い消防本部もあるので、何度も言いますが受験する自治体の試験内容をしっかり確認しましょう。
適正試験
適正試験は試験というより検査に近いです。
消防という仕事に適正があるか判断します。
この結果で合否が左右されることはありません。
口述試験
口述試験は試験という名前がついていますが面接です。
『なぜ、消防士になりたいのか?』『たくさんある消防本部でなぜ、ここを受験したのか?』
など、聞かれそうな内容は事前に準備しておきましょう。
私は、口述試験はチャンスゾーンだと思っています。自分を存分にアピールできる唯一のポイントです。
自分がどれだけ消防士なりたいのか、熱い気持ちを面接官に伝えてください。
面接官も同じ人間です。熱い気持ちが伝われば、こんなにも情熱がある、この人を採用したいと思いますよね?
面接官を味方につける。これがとても重要です。
身体検査
身体検査では、身体に異常がないか確認します。
消防士は身体が資本の仕事です。なので、このような試験が含まれています。
消防採用事情
最近の消防採用事情についてお話します。
11年前に採用された時と今では、採用条件や職場環境等に変化があり消防という環境も今の時代に対応してきたのかなと思っています。
採用試験を受ける前に現状の採用関係情報をお話します。
消防本部の併願
消防職を受験する際には試験日が重複していなければ、他の消防本部を受験できます。
試験慣れするために他の消防本部の採用試験を受験するのもアリです。
また、公務員試験に慣れるために自衛隊や海上保安等の試験を受けるのもいいかもしれません。
女性消防職員
女性消防吏員の活躍推進の観点から消防庁として、令和8年度当初までに女性消防吏員比率を5%引き上げることを共通目標としています。
そのため全国的にも女性消防職員の割合は年々増加しており、他消防本部の女性消防職員の交流会等も実施されており働きやす環境の構築がなされています。
受験年齢の上限引き上げ
これまでは、採用試験を受験できる年齢が17歳(高卒)から26歳程度までというのが一般的でしたが、近年全国的に受験年齢の上限が引き上げられています。
東京消防庁では受験年齢の上限は36歳未満となっており社会人経験者の受験機会を増やすために年齢の上限を引き上げる傾向にあるみたいです。
よくあるパターンは東京消防庁や政令指定都市の消防本部で採用され、一定年数働き、辞めて地元の消防本部で採用されるケースです。
このような人は、現場経験があり即戦力となるため重宝されることは間違いありません。消防経験枠といった採用枠もある消防本部もあるみたいです。
定員割れ
全国に消防本部は約700施設あり、定員割れしてる消防本部もあります。
地方、言わば田舎の消防本部は定員割れしている消防本部も多数見受けられます。特に離島では定員割れしている消防本部も多数あるようです。
例えば、南の島に定員割れしている消防本部があり趣味がサーフィンやスキューバダイビングの人は受ける価値はあるかもしれません。
どこの消防本部で働いてもすることは同じです。市民の生命、身体、財産を守ること。
地元以外の消防本部で働くことも視野に入れてみてはどうでしょうか?
まとめ
簡単ですが、今回は消防士になるための手順を書かせていただきました。
まとめです。
消防士になるには地方公務員試験の消防職に合格する必要がある。
受験する消防本部の試験内容を確認する。
以上です。
消防士を目指す皆さんが無事合格できるよう、これからも情報発信していけたらと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

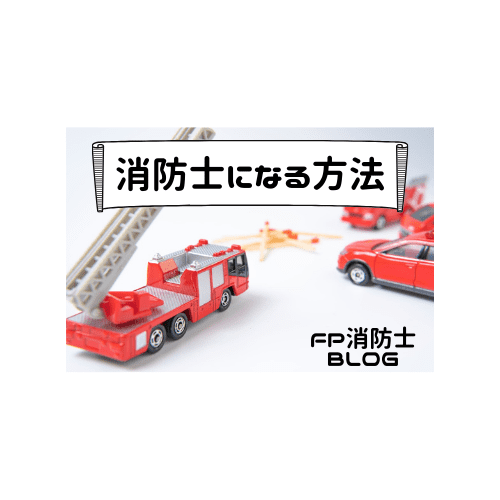




コメント