こんにちは、FP消防士と言います。
今回は、公務員試験(消防職)を詳しく解説していきます。
この記事は
公務員試験って何するの?
公務員試験(消防職)の内容が知りたい!!
このような人のための記事となっています。
結論
消防士になるために突破しなければならない試験の項目は以下の通りです。
教養試験
体力試験
作文試験
口述試験
適正試験
身体検査
自治体によって若干異なる部分もありますが、概ね試験項目はこのようになっています。
自分が受験する自治体の試験内容を必ず確認しましょう。
試験では教養試験、体力試験、作文試験、口述試験、適正試験の試験があることが分かりましたが、具体的な試験の中身が気になりますよね。
では、ひとつずつ詳しく解説していきます。
教養試験
教養試験の範囲はとても広く、公務員として必要な知識や学力が必要となっています。
ただ体力に自信があるだけでは、消防士にはなれません・・・。
地方の消防士はオールマイティーに仕事をしないといけません。
ぶっちゃけ、事務作業の方が多いです。
とは言え、公務員として必要な知識や学力ってどの程度?と思われますよね。
公務員として必要な知識、学力 = 教養試験の試験範囲だと思ってください。
公務員試験対策の問題集を見たことがある人なら分かるでしょう・・・。
基本的な教科の全部ですね!!
基本的な教科って何かというと、地理、数学、古典、現代文、化学 etc….。
私も消防士になろうと決めて試験範囲を見て驚きました。
ですが、公務員試験は試験範囲が広いだけではなく、重要視されている科目は別にあるんです。
その科目は文章理解と数的処理です!
この中でも文章理解と数的処理は解答数に占める割合が6割以上となっていますので対策が必要です。
対策として、私は何度も地方公務員試験の過去問を周回しました。
そして、試験慣れするために自衛隊や海上保安庁などの採用試験を受験し、本命の消防本部の採用試験対策をしました。
試験はマークシート方式で4択または5択の選択式となっています。
分からない問題があっても、点数になる可能性はあります。
体力試験
消防士は身体が資本の仕事です。
ある程度は体力がないと仕事にならないことから体力試験が組み込まれています。
何度も言いますが、自治体によって種目が異なります。
受験する自治体の種目にあったトレーニングをしましょう。
また、体力試験の会場は屋外なのか屋内なのか事前に確認しておきましょう。
なぜなら、会場に応じて体育館シューズやランニングシューズを持参しなければならないからです。
ここで注意点があります。
体力試験会場が屋外開催予定の場合に当日に雨が降り、急遽、屋内で体力試験を行う場合もあります。
天気予報はこまめにチェックしましょう。
体力試験の内容は以下の通りです。
走力系
1km走、1500m走、5分間走、100m走、50m走、シャトルラン
走力系は、この中に含まれている種目のどれかを実施することになると思います。
長距離と短距離では大きな違いですよね。
自治体によっては、長距離と短距離どちらも試験項目に入っているところもあります。
消防士の現場では、持久力も瞬発力のどちらも必要なので鍛えることは必要ですが、まずは体力試験に向けてトレーニングをすることをオススメします。
瞬発力系
反復横跳び、立ち三段跳び、垂直跳び、立ち幅跳び
瞬発力系の種目は、一般的に高校で実施する体力測定の内容から馴染みのない種目もありますので対策が必要です。
筋力系
懸垂、上体起こし、腕立て伏せ、背筋力、握力
体力試験は、自治体ごとに若干の種目の差はありますが、ほとんどの消防本部に必ずある項目があります。
それは『懸垂』です。
私も消防士になり、過去何度も採用試験を見てきましたが、体力試験の懸垂は他の種目に比べて注目されています。
順手、逆手でそれぞれ最低でも20回はできるようになりましょう。
『肘をしっかり伸ばし、勢いをつけず顎を鉄棒より上に』
これで1回です。肘が曲がっていたり顎が鉄棒まで届いていなかったりすると回数にカウントされない場合がありますので注意が必要です。
誰が見ても、完璧な懸垂を目指しましょう。
女性の場合は、男性と筋力量や体格に差がありますので、斜め懸垂や膝付き腕立て伏せを取り入れている消防本部もあります。
ただ、多少は男女でこのように試験の違いがありますが、男性と全く同じ内容の消防本部もあるようです。
作文試験
作文試験の試験時間は1時間から1時間半程度で800字から1,200字程度です。
試験内容としては、消防業務に関すること(火災、救急、救助)、地域防災について、自助・共助・公助について、チームワークに関すること、etc….。
消防本部のホームページに過去に実際出題された題材を掲載している消防本部もあります。その題材で自分がどこまで作文が書けるか挑戦してみましょう。
題材は様々ですが、できれば作文の中に『消防士になりたい!』という熱い気持ちを組み込めるように書きましょう。
なぜなら、作文試験はマークシートの試験とは違い人の目で採点されるということです。
消防士になりたいという熱い気持ちが試験官に伝わるかもしれません。
口述試験
口述試験って何するの??と思われるかもしれませんが面接です。
消防本部によって、個人面接か集団面接か違いがありますので、採用試験を受ける消防本部はどちらの面接形式か確認しておきましょう。
当たり前のことですが、採用試験に相応しい格好で臨みましょう。
髪型は、できれば短髪の方が印象は良いと思います。
この口述試験で一番大事なことは、ハキハキと大きな声で受け答えをすることです。
消防に合格すると半年間、消防学校というところに入校し、消防のイロハを学びます。消防学校での点呼や訓練は必ず『大きな声』で行います。
『大きな声を出す』これは消防の基本中の基本なのです。
なので、ハキハキと大きな声で受け答えしている方が好印象でしょう。
口述試験で聞かれそうなことは事前に対策しておきましょう。
『なぜ、消防士になりたいのですか?』
『ここの消防本部を選んだ理由は何ですか?』
『消防という仕事についてどう思いますか?』
概ね、王道の質問はこのようなところでしょうか。
口述試験に役立つ最近の消防事情
近年、若者の早期退職が増加傾向にあり消防もこの限りではありません。
実際、私の周りにも辞めていった人達がいます。
よくあるパターンは、東京消防庁や政令指定都市等の規模の大きな消防本部で採用され、何年後かに退職、地元に帰り、地元消防本部に採用されるケースです。逆のパターンも然りです。
地元の消防本部側からすると現場経験のある人材は即戦力!!欲しい人材です。
ですが、逆の立場で考えてみましょう。公費で消防学校に入校させ即戦力として育ててきた職員が退職した場合、損失でしかありませんよね。優秀な人材を失うわけですから避けたいはずです。
なので、消防本部で長く働いてくれる人材を探しています。
採用されて1〜2年で辞めそうな人材を採用するメリットがありません。
ということは、長く働けることはアピールポイントになります。
口述試験の限られた時間内に、いかに自分をアピールできるかが勝負です!
まず、覚えておいて欲しいことは面接官は消防士といことです。
これから採用されて、上司となり得る人です。
この人に一緒に働きたいと思わせることが大切です。
口述試験は、消防士なりたい熱い気持ちを面接官に伝えるチャンスゾーンです。有効に使いましょう!!
適正試験
適正試験、これは試験というより検査に近い項目です。
仕事上、過酷な現場で活動することは少なくありません。なので、このような現場に対してストレス耐性があるか?
また、消防は24時間の集団生活になりますので、協調性はあるか?
などなど、消防の仕事をしていく上で適正があるかチェックする検査となっています。
身構えずにリラックスして、適正試験を受けましょう。
適正試験の結果で合否が左右されることはまず無いと言えるので安心してください。
身体検査
身体検査では、視力、聴力、色覚等の検査を行います。
体が主体の仕事なので、身体検査は重要なものです。
自治体によってては、裸眼視力に制限があるところもあるので注意が必要です。
まとめ
今回は、公務員試験(消防職)の内容を解説しました。
長々と書きましたが重要な点は以下の通りです。
自治体によって採用試験の内容が異なるのでホームページ等で必ず確認する。
教養試験はマークシート方式。
作文試験は1時間から1時間半で800字から1,200字程度。
適正試験の結果で合否は決まらない。
いかがでしたか?
少しは公務員試験(消防職)について理解が深まったと思います。
以上です。
今後も消防士を目指す皆さんが、無事合格できるよう消防に関する情報を発信していきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

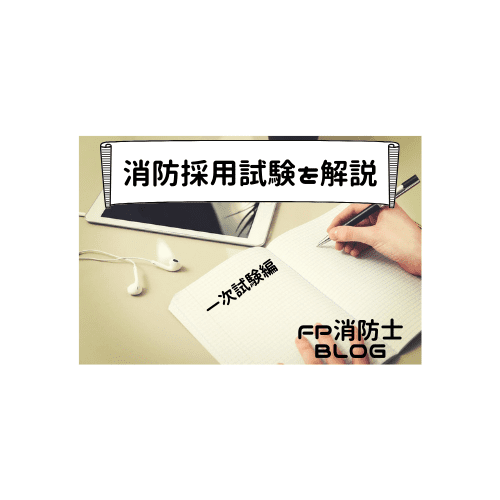





コメント