こんにちはFP消防士です。
今回は、今まで参加してきた自主研修会や訓練会をご紹介します。
もちろん全て自費で参加しておりますのでご安心を!
この記事は
そもそも研修会や勉強会って何があるの?
FP消防士が今まで参加してきた研修会や勉強会は何があるの?
このような内容が知りたい人向けの内容となっています。
最近は、仕事の都合で全く行けてないですが、暇が見つかれば行きたいですね!
結論
私が今までに参加してきた研修会や勉強会をご紹介します。
Rescue3 TRR-T
Rescue3 SRT-1
rescue DAYS.JP
SCRM ベーシックコース
他にも県内の有志で開催された研修会や訓練会もありましたが、キリがないのでこの4つに絞りました。
私の県では、有志で行なっている研修会や訓練会も多くあり過去にはFFS、トレンチレスキュー、ドア開放といった内容のものが開催されています。
私も100%参加とは言えませんが、ほとんど参加経験有りです。
TRR-T
この講習会はテクニカルロープレスキューテクニシャンレベルというRescue3社が開催しているロープレスキューの講習会になります。
初めて参加した講習会ですね。
この講習はロープレスキューの基礎を学ぶ講習会となっています。
期間は3日間となっており、座学と実技があり効果測定もあります。
効果測定といっても講習会を真面目に受けていれば簡単なものなので安心してください。
座学では、安全管理や指揮統制、ロープレスキューに関する知識などを徹底的に学習します。
実技では、各種結索から資機材の取り扱い要領、チームレスキュー訓練などがあります。
この講習を修了した人にはRescue3社が発行している国際認定資格証とワッペンがもらえます。
ロープレスキューについてこれから学びたいと思っているか方には良い講習会だと思います。
最近では、ロープレスキューも注目度が上がっていますよね。
台湾で開催されている大会「橋 Ch’iao」やベルギーで開催されている大会「GrimpDay」などがあります。
GRIMP JAPANも開催されかなり盛り上がっています。
知り合いに台湾やベルギーで実際に大会に出場された方もいるので話を聞き、一緒にロープレスキューのトレーニングすることで刺激をもらっているところです。
最近は、全く行けてませんが・・・。
SRT-1
この講習会はスイフトウォーターレスキューテクニシャン レベル1というRescue3社が開催しているスイフトウォーターレスキューの講習会になります。
急流救助に特化した講習会となっています。
この講習会に参加したいのであれば、ある程度泳げないとキツイと思います。
TRR-Tと同じで期間は3日間となっており、座学と実技があり効果測定もあります。
こちらも効果測定はありますが講習会を真面目に受けていれば簡単なものなので安心してください。
座学の内容はTRR-Tと同じ内容のものもありましたが、それに加えて急流に関する知識などを学びます。
ここでは、ロープレスキューの知識も少なからず必要になってきます。
実技では、急流での泳ぎ方や溺者の救助方法、スローバックを用いた救助要領を行います。
初日は、かなり川の水を飲むことになりました・・・。
まぁ、行けば分かります!!
うちの管内に急流はないし、必要ない知識かな?
と思っている方もいるのではないでしょうか??
そんなことはありません。
大雨、洪水により水位が上昇、それに伴い急流に似た状況が街中に発生する可能性は十分にあります。
知らない、できないでは済まされませんよ。
と思うところですね。
rescue DAYS.JP
この講習会は交通救助に関するもので、レスキューツールメーカーのWEBER社の協力のもと実施されています。
消防本部によって油圧資機材のメーカーは異なると思います。
代表的なもので言うとWEBER(ウェーバー)、 LUKAS(ルーカス)、 Holmatro (ホルマトロ)といったところでしょうか。
この中の一社、WEBER社のインストラクターによるレスキュー理論、事故現場を再現した環境での実技訓練を行います。
私が行った時は、3日間の講習会で開催場所は新潟県長岡市でした。
座学で車の構造、電気自動車の留意点などを学びました。
かなり勉強になりました!!
実技では、広い会場に今から破壊される予定の車が70台程度配置されていました。
しかも色んなパターンで配置されており、横転、転覆は予想はできましたが・・・。
車が倒立してる!!!
車が立体駐車場から落下した事故などで見る光景がありました。
「すげー!!!!」の言葉しか出てこなかったですね。
実技は、何班かに分かれてブースごとに事故パターンの想定が付与されており実際に破壊、救助すると言うものでした。
WEBER社のインストラクターはドイツ人の方が多く、車両破壊の説明、実技の要領は通訳を通して説明されていました。
普段の訓練でこれだけの数の車を破壊することができないので、とても有意義な訓練となりました。
CSRM ベーシックコース
これは、Confined Space Rescue & Medicineの略称で狭隘空間における救助・救急・医療のことを指します。
震災時の倒壊建物からの逃げ遅れの要救助者を救助することに必要な知識や技術を学びます。
兵庫県三木市で開催されたものに参加し、期間は2日間でした。
座学でCSRMの基礎知識を学び、実技では班ごとに想定訓練を行います。
コースがいくつも設定されており、実際に狭隘空間でのレスキューを行います。
CSRMに必要なPPEは、準備しておく必要があります。
耳栓、防塵マスク、ゴーグル、肘膝サポーター、etc・・・・。
ヘルメットを外さないと通らないような狭い空間もあります。
その他にはCSRMのMの頭文字であるMedicine、つまり救急・医療に関する知識も必要です。
看護師の方も大勢参加されていますので、消防だけが参加している講習会ではありません。
DMATに在籍の方や自衛隊に配属されている看護師の方など様々です。
私がCSRMに参加した時の小隊のグループラインがあるのですが、今だに分からないことなど聞いたりします。
まとめ
今回は、私が以前参加した講習会についてざっくりお話しました。
講習会で学んだ知識、技術はとても重要ですが、講習会を受けた後もスキルをアップグレードしていかないと意味がありません。
このような講習会で学んだ知識、技術と同じくらいに大事なものもあります。
それは、講習会で知り合った方々です。
このような繋がりは、とても大切で貴重なものです。
普通に仕事をしていると、他県の本部の方と関わることは少ないと思います。
一歩踏み出して、自己のスキルアップに努めてみませんか?
まとめです。
最新の知識、技術を身をもって学ぶことができる。
他本部の人達と繋がりを持てることは、スキルアップと同様に貴重なこと。
自分に興味がある講習会もあると思いますので、探してみてはいかがですか?
以上です。



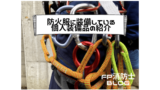


コメント